| 初代−第50代 (奈良時代以前) |
|
即位 |
漢風諡号 |
読み方 |
補 足 |
| (即位の年号に関して、21代雄略天皇以前の斜字のものは、推古天皇の崩年干支から推測したもので定かではありません) |
| 1 |
|
神武 |
じんむ |
日本書紀では、BC660年に即位。 |
| 2 |
|
綏靖 |
すいぜい |
|
| 3 |
|
安寧 |
あんねい |
|
| 4 |
|
懿徳 |
いとく |
|
| 5 |
|
孝昭 |
こうしょう |
|
| 6 |
|
孝安 |
こうあん |
|
| 7 |
|
孝霊 |
こうれい |
皇子=吉備津彦 |
| 8 |
|
孝元 |
こうげん |
|
| 9 |
|
開化 |
かいか |
|
| 10 |
(307) |
崇神 |
すじん |
実在したといわれる最初の天皇。崩年318? |
| 11 |
|
垂仁 |
すいにん |
|
| 12 |
|
景行 |
けいこう |
皇子=大和武尊。大和武尊は、幼名を小碓命(おうすのみこと)といい,兄の大碓命(おおうすのみこと)とは双子の兄弟とも言われています。 |
| 13 |
|
成務 |
せいむ |
|
| 14 |
|
仲哀 |
ちゅうあい |
|
| 15 |
(394) |
応神 |
おうじん |
母は神功皇后。 |
| 16 |
(427) |
仁徳 |
にんとく |
|
| 17 |
(432) |
履中 |
りちゅう |
|
| 18 |
(437) |
反正 |
はんぜい |
|
| 19 |
(454) |
允恭 |
いんぎょう |
|
| 20 |
|
安康 |
あんこう |
|
| 21 |
471 |
雄略 |
ゆうりゃく |
ワカタケルオオキミ。
吉備氏と争う。雄略天皇7年に吉備上道(かみつみち)臣田狭(吉備田狭)が新羅と結託して朝廷に反乱を起こす(吉備氏の乱)。 |
| 22 |
|
清寧 |
せいねい |
|
| 23 |
|
顕宗 |
けんぞう |
|
| 24 |
|
仁賢 |
にんけん |
|
| 25 |
|
武烈 |
ぶれつ |
|
| 26 |
507 |
継体 |
けいたい |
越前出身、大和に入るまで20年かかった。 |
| 27 |
531 |
安閑 |
あんかん |
二朝並立時代 |
| 28 |
535 |
宣化 |
せんか |
二朝並立時代 |
| 29 |
531 |
欽明 |
きんめい |
二朝並立時代 |
| 30 |
572 |
敏達 |
びだつ |
|
| 31 |
586 |
用明 |
ようめい |
聖徳太子の父。 |
| 32 |
588 |
崇峻 |
すしゅん |
蘇我馬子によって暗殺された。 |
| 33 |
593 |
推古 |
すいこ |
女帝。摂政に甥の聖徳太子を立てる。 |
| 34 |
629 |
舒明 |
じょめい |
|
| 35 |
642 |
皇極 |
こうぎょく |
女帝 (重祚し、37代斉明天皇となる) |
| 36 |
645 |
孝徳 |
こうとく |
軽皇子。難波宮に置き去りにされた。 |
| 37 |
655 |
斉明 |
さいめい |
女帝(=皇極天皇)。各種の外征を行う。 |
| 38 |
662 |
天智 |
てんじ |
中大兄皇子。藤原鎌足と大化の改新。近江京遷都。 |
| 39 |
672 |
弘文 |
こうぶん |
大友皇子。大海人皇子と対立。 |
| 40 |
673 |
天武 |
てんむ |
大海人皇子。壬申の乱で、弘文天皇を倒す。飛鳥宮遷都。 |
| 41 |
690 |
持統 |
じとう |
女帝。天智天皇の第2女。天武天皇皇后。藤原京遷都。 |
| 42 |
697 |
文武 |
もんむ |
天武の孫。 |
| 43 |
707 |
元明 |
げんみょう |
女帝。天武の子の妻。平城京遷都。 |
| 44 |
715 |
元正 |
げんしょう |
女帝。天武の孫。 |
| 45 |
724 |
聖武 |
しょうむ |
大仏建立を行った。 |
| 46 |
749 |
孝謙 |
こうけん |
女帝。(重祚し、48代称徳天皇となる) |
| 47 |
758 |
淳仁 |
じゅんじん |
|
| 48 |
764 |
称徳 |
しょうとく |
女帝(=孝謙天皇)。道鏡譲位事件。 |
| 49 |
770 |
光仁 |
こうじん |
天智天皇の孫。9代にわたる天武朝の終焉。 |
| 50 |
781 |
桓武 |
かんむ |
長岡京遷都。平安京遷都。 |
|
| 第51代−第81代 (平安時代) |
|
即位 |
漢風諡号 |
|
|
| 51 |
806 |
平城 |
へいぜい |
|
| 52 |
809 |
嵯峨 |
さが |
810年に平城天皇が復位を試みた「薬子の変」が発生。 |
| 53 |
823 |
淳和 |
じゅんな |
|
| 54 |
833 |
仁明 |
にんみょう |
|
| 55 |
850 |
文徳 |
もんとく |
|
| 56 |
858 |
清和 |
せいわ |
清和源氏の祖。 |
| 57 |
876 |
陽成 |
ようぜい |
|
| 58 |
884 |
光孝 |
こうこう |
|
| 59 |
887 |
宇多 |
うだ |
藤原氏を外戚としない天皇。藤原時平と菅原道真を重用した(寛平の治)。 |
| 60 |
897 |
醍醐 |
だいご |
摂関を置かず形式上の親政を行っていたため、後世「延喜の治」と崇められた。
昌泰4年(901年)、時平の讒言を聞き菅原道真を大宰権帥に貶めた(昌泰の変)。 |
| 61 |
930 |
朱雀 |
すざく |
在位中に平将門・藤原純友の承平・天慶の乱(935年 - 940年)が起こる。 |
| 62 |
946 |
村上 |
むらかみ |
|
| 63 |
967 |
冷泉 |
れいぜい |
|
| 64 |
969 |
円融 |
えんゆう |
|
| 65 |
984 |
花山 |
かざん |
|
| 66 |
986 |
一条 |
いちじょう |
|
| 67 |
1011 |
三条 |
さんじょう |
|
| 68 |
1016 |
後一条 |
ごいちじょう |
|
| 69 |
1036 |
後朱雀 |
ごすざく |
|
| 70 |
1045 |
後冷泉 |
ごれいぜい |
|
| 71 |
1068 |
後三条 |
ごさんじょう |
宇多天皇以来170年ぶりの藤原氏を外戚としない天皇となった |
| 72 |
1073 |
白河 |
しらかわ |
|
| 73 |
1086 |
堀河 |
ほりかわ |
|
| 74 |
1107 |
鳥羽 |
とば |
|
| 75 |
1123 |
崇徳 |
すとく |
|
| 76 |
1142 |
近衛 |
このえ |
|
| 77 |
1155 |
後白河 |
ごしらかわ |
|
| 78 |
1158 |
二条 |
にじょう |
|
| 79 |
1165 |
六条 |
ろくじょう |
|
| 80 |
1168 |
高倉 |
|
|
| 81 |
1180 |
安徳 |
あんとく |
2歳で即位。壇ノ浦の戦いで入水。 |
|
 |
「ファンタジ−米子・山陰の古代史」は、よなごキッズ.COMの姉妹サイトです |
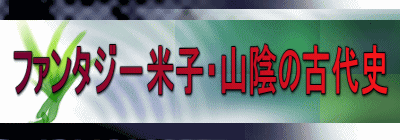  |
|